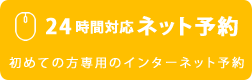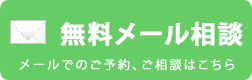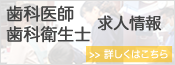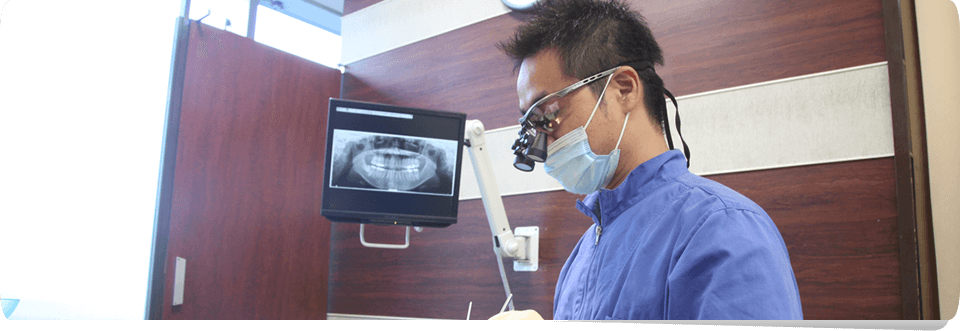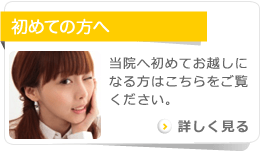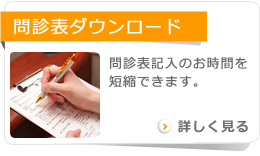こんにちは、関原デンタルクリニックです。
歯周病は歯を支える組織が細菌によって破壊される病気で、
日本の成人の約7割が罹患しているともいわれる非常に一般的な疾患です。
初期段階では歯ぐきの腫れや出血といった軽い症状から始まりますが、
進行すると歯を支える骨(歯槽骨)が溶け、
最終的には歯が抜け落ちてしまうこともあります。
今回は、特に女性が歯周病になりやすい理由に注目し、
骨が溶ける仕組みや予防のポイントについてご紹介します。
歯周病とは

歯周病は、歯と歯ぐきの間に溜まったプラーク(歯垢)に含まれる細菌が原因で、
歯ぐきや歯槽骨が徐々に破壊される病気です。主な原因は、
プラーク内の細菌が作り出す毒素や炎症物質が歯ぐきに炎症を引き起こし、
免疫反応が過剰に働くことで組織が破壊されることです。
初期の「歯肉炎」と進行した「歯周炎」に大別され、
歯周炎になると骨の破壊が進むため、早期発見・治療が大切です。
歯が溶けるのはなぜ?

歯周病が進行すると歯槽骨が溶ける原因は、免疫反応が過剰に働くことにあります。
細菌が出す毒素に対抗するため免疫細胞が炎症を引き起こしますが、
このときに放出されるサイトカインという物質が骨を溶かす破骨細胞を活性化させてしまうのです。
特に、骨の代謝に関わるRANKL(ランクル)というタンパク質が
過剰に生成されると破骨細胞の働きがさらに活発化し、
骨が急速に失われることがあります。
また、喫煙も歯周病のリスクを高める要因です。
タバコに含まれる有害物質は歯ぐきへの血流を減少させ、
免疫力を低下させるため細菌に対する抵抗力が弱くなり、
歯周病の進行が早まるとされています。したがって、禁煙も歯周病予防には非常に効果的です。
微生物との上手なつきあい方

歯周病の予防には、口内の細菌との適切なバランスを保つことが大切です。毎日の正しいブラッシングやデンタルフロスの使用、定期的な歯科検診が効果的です。
さらに、食事も重要な要素です。野菜や果物に含まれる食物繊維は噛む回数を増やし、唾液の分泌を促進します。唾液は口内の細菌を洗い流し酸性の環境を中和する役割もあるため、こまめな水分補給やよく噛む習慣も歯周病予防に役立ちます。特にキシリトールは虫歯予防に効果があることが知られていますが、歯周病の原因菌の活動も抑える働きがあるためガムやタブレットでの摂取も効果的です。
まとめ
歯周病は気づかぬうちに進行してしまうことが多い病気ですが、
適切なケアと予防で大幅にリスクを減らすことができます。
特に女性はホルモンバランスの変化により歯周病になりやすい傾向があるため、
定期的なメンテナンスと早期発見が大切です。
気になる症状がある方は、ぜひお気軽に当院にご相談ください。
日付: 2025年5月12日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ, 女性ホルモンと歯周病