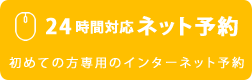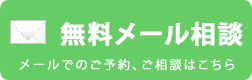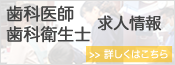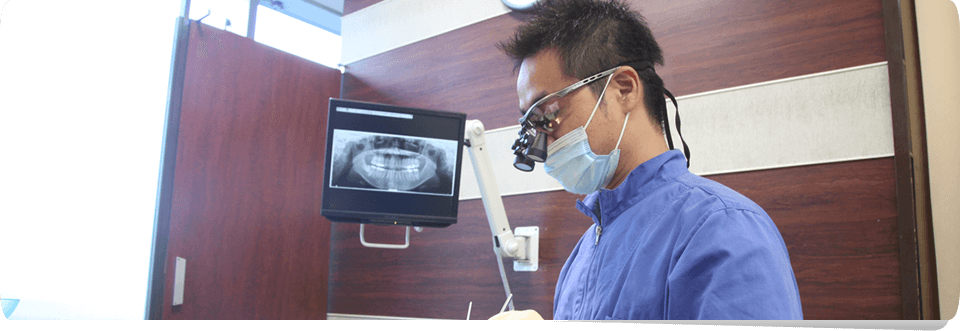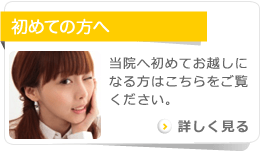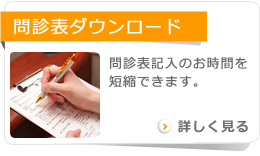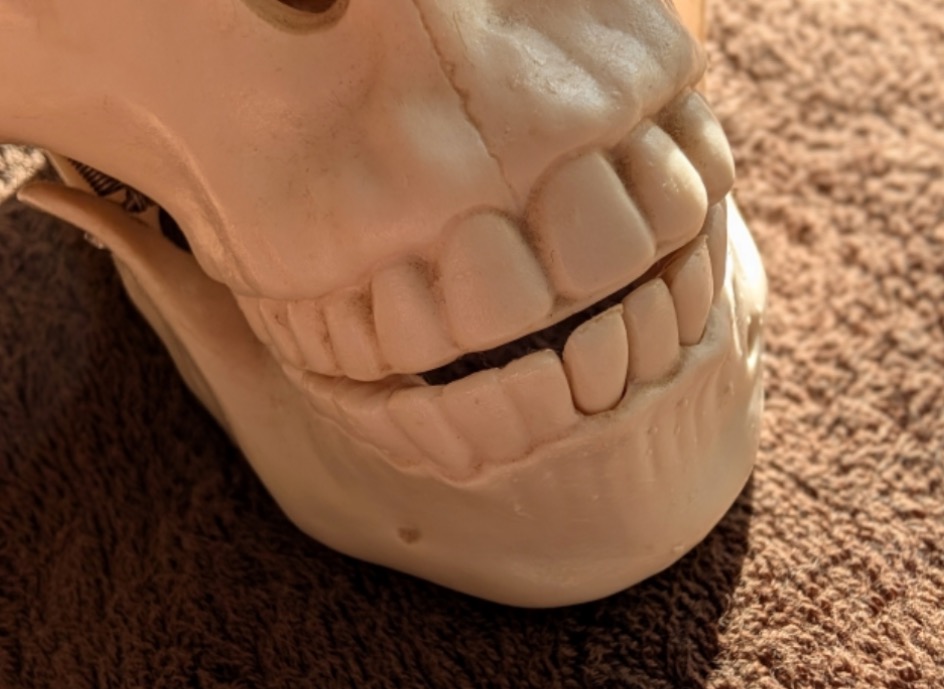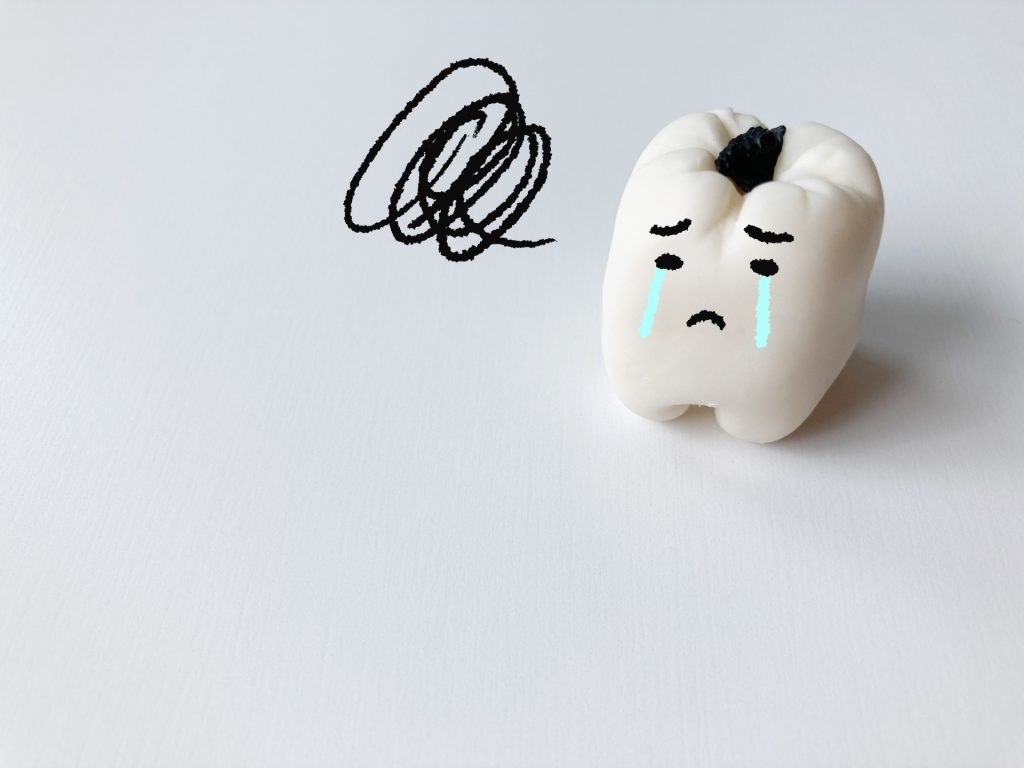こんにちは、関原デンタルクリニックです。
「冷たいものが歯にしみる」
「最近、歯がなんだか黄ばんできた気がする…」そんなお悩みはありませんか?
その症状、実は虫歯ではなく「酸蝕症(さんしょくしょう)」によるものかもしれません。
酸蝕症は、進行すると歯の健康に影響を及ぼす可能性がある、
私たちの生活習慣に潜む疾患です。
今回は、この気づきにくい「酸蝕症」の特徴と、
今日からできる予防のポイントについてご紹介いたします。

気づきにくい「酸蝕症」とは?
酸蝕症とは、「酸」によって歯の表面が少しずつ溶かされていく状態のことを指します。
歯の表面は「エナメル質」という非常に硬い組織で覆われていますが、
このエナメル質は酸にとても弱く、酸性の飲食物と長時間接すると、
徐々に溶けてしまうのです。
「虫歯」とは原因が異なります。
【虫歯】は、虫歯菌が食べ物に含まれる糖を分解して酸を出し、
その酸が歯を溶かして穴があくことで起こります。
一方で酸蝕症は、飲食物に含まれる酸が歯の表面に直接作用し、
広い範囲でエナメル質を溶かしてしまうことが原因です。
【酸蝕症】は、虫歯のようにすぐに痛みが出ることが少ないため、
気づかないうちに進行してしまうこともあります。
酸蝕症を引き起こす主な2つの原因

① 外から入る「酸」(外因性)
多くの場合、日々の食生活が原因です。
口の中が酸性状態のままだと、エナメル質が徐々に溶けてしまいます。
酸性度が高い代表的なものは以下のとおりです。
〈飲料〉
・炭酸飲料・スポーツドリンク・栄養ドリンク・ワイン・ビール
〈食品〉
・柑橘類・梅干し・黒酢
〈健康食品〉
・黒酢ドリンク・ビタミンCサプリメント など
一部の食品・飲料は体に良いとされることがありますが、
摂取の仕方によっては歯に負担をかけることがあります。
② 体内からの「酸」(内因性)
胃酸が逆流する「逆流性食道炎」や、つわりなどによる嘔吐も原因になります。
強い酸である胃酸が口腔内に達することで、歯が溶けることがあります。
胸やけなどの症状が続く方は内科受診もご検討ください。
酸蝕症予防の4つの習慣

1. 飲食の工夫で酸をコントロール
酸性の食品や飲料を摂った後は水やお茶で口をゆすぐようにしましょう。
「だらだら食べ・飲み」を控え、時間を決めて飲食することも大切です。
また、就寝中は唾液が減るため、
寝る前の飲食は控えることも酸蝕症を防ぐことにつながります。
2. 歯磨きのタイミングに注意
酸性のものを摂取した直後はエナメル質が柔らかくなっています。
すぐに歯を磨くと表面を傷つけてしまうこともあります。
食後は水でゆすぎ、30分〜1時間後にやさしく歯を磨きましょう。
3. フッ素で歯を強く
再石灰化をサポートするフッ素入りの歯磨き粉を使うことで、
酸に強い歯づくりをサポートできます。
ぜひ毎日のケアに取り入れましょう。
4. 定期検診で早期発見
初期の酸蝕症は自覚しにくいからこそ、
歯科での定期チェックとプロによるクリーニングを受けることが大切です。
高濃度のフッ素塗布は、酸蝕症予防に効果が期待されています。
まとめ
酸蝕症は身近な飲食や生活習慣が関係するため、
自覚がないまま進行することがあります。しかし、
日々の意識と適切なケアで予防・対策は十分に可能です。
当院では、お一人おひとりのお口の状態に合わせた
丁寧なカウンセリングを行っております。
「歯がしみる」「見た目が気になる」など、
少しでも気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
日付: 2025年7月3日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ, その「しみる歯」、虫歯じゃないかも?気づかぬうちに歯が溶ける「酸蝕症」の原因と対策