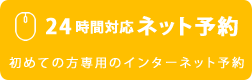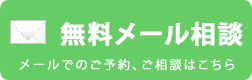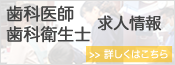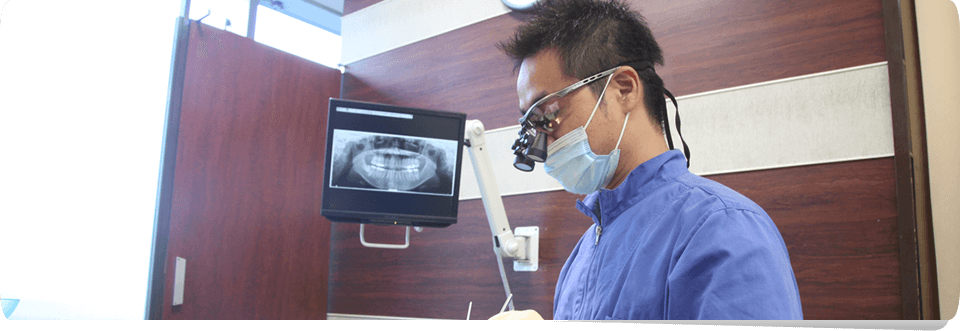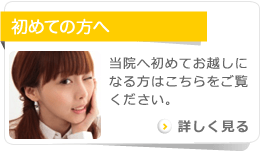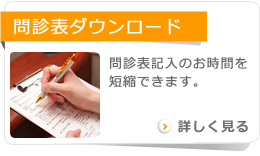こんにちは、関原デンタルクリニックです。
「むし歯や歯周病になりやすいと言われた」
「しっかり歯磨きをしているのに口内トラブルが続く」そんなお悩みを抱えていませんか?
お口の健康は、歯の表面や歯ぐきの状態だけでなく、
唾液の質や量にも大きく関係しています。
その唾液の状態を客観的に調べられるのが「唾液検査」です。
今回は、唾液検査でわかることやメリット・デメリット、注意点まで詳しくご紹介します。

唾液検査とは?
唾液検査は、少量の唾液を採取し、
お口の健康状態やむし歯・歯周病のリスクを分析する検査です。
唾液には消化や洗浄、細菌の増殖を抑える働きがあり、
その量や性質を調べることで、口内環境の健康度やトラブルの起こりやすさがわかります。
方法は簡単で、専用容器に唾液をためるか、
無味のパラフィンを噛んで採取し、機器や試薬で測定します。
唾液検査でわかること

唾液検査では、お口の健康に関わる複数の項目を同時にチェックできます。
測定結果を総合的に見ることで、むし歯や歯周病、
口臭などのリスクを客観的に把握できます。
◎むし歯に関与する細菌(機器により指標や表示は異なります)
むし歯の原因となる細菌の有無や量を測定します。
菌の数が多いほど、むし歯の発症・進行リスクが高くなります。
◎酸性度(pH)
お口の中の酸性度を調べます。酸性に傾くと歯の表面が溶けやすくなり、
むし歯が進行しやすくなります。
◎緩衝能(酸を中和する力)
酸性化した口内環境を中和する能力を測ります。
緩衝能が高いとむし歯になりにくく、低いとリスクが高まります。
◎白血球
歯ぐきの炎症や出血の可能性を示す指標です。
数値が高い場合、歯周病や歯肉炎の兆候がある可能性があります。
◎タンパク質
歯ぐきからの出血や炎症に関係し、歯周病リスクの目安となります。
高値の場合は歯ぐきの健康状態に注意が必要です。
◎アンモニア
お口の中の清潔度や口臭の原因に関わる成分です。
数値が高いと、口臭や細菌の繁殖が起こりやすい状態と考えられます。
◎唾液分泌量(一部の検査で測定)
唾液の量は自浄作用や口内の保護機能に直結します。
少ない場合はドライマウスや口臭、むし歯のリスクが高まります。
* これらの項目を組み合わせて評価することで、現時点でのお口の健康度を把握し、
一人ひとりに合った予防方法や生活習慣の改善につなげられます。
唾液検査のメリットとデメリット

【メリット】
・お口の状態を数値で把握でき、リスクがわかる
・結果に合わせた予防やケア方法を提案できる
・痛みや不快感が少なく短時間で実施可能
・改善が数値で見えて、ケアの意欲が高まる
【デメリット】
・食事や体調など、その日の状態に左右されやすい
・むし歯や歯周病の有無を確定するには歯科医師の診察や検査が別途必要
注意点
唾液検査で正確な結果を得るために以下の点に注意しましょう。
・検査の2時間以内は飲食・歯磨き・喫煙を控える
・アルコール入り洗口剤は前日夜(約12時間前)以降は使用しない
・検査当日はできるだけ普段通りの体調で臨む
本検査はスクリーニングを目的としており、診断や治療の代替にはなりません。
結果は「現時点でのお口の環境」を示し、生活習慣やケアで数値は変化します。
継続的なケアと定期的な検査が大切です。
まとめ
唾液検査は、むし歯や歯周病のリスクを客観的に把握できる便利な方法です。
唾液の量や質、細菌の有無などを調べることで、
自分に合った予防法を選びやすくなります。
当院では、検査結果をわかりやすくご説明し、
患者様一人ひとりに合わせたケア方法をご提案しています。
お口の健康を守るために、気になる方はぜひ一度ご相談ください。
日付: 2025年9月1日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ, 唾液検査でわかるお口の健康度と予防への活かし方