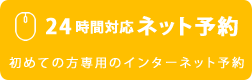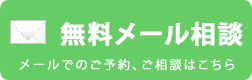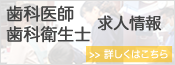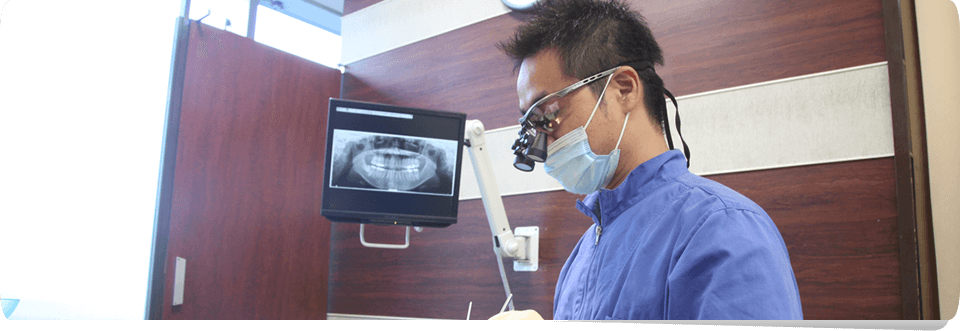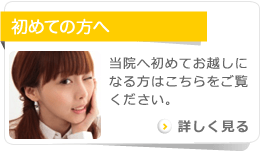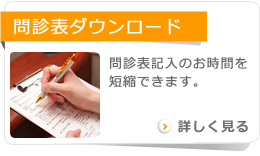こんにちは、関原デンタルクリニックです。
歯科で治療を受けたあと、「お薬出しておきますね」と言われて、
痛み止めや抗菌薬をもらったことがある方も多いと思います。
でも、「これは何のための薬?」「どう飲めばいいの?」と疑問に思うことはありませんか?
今回は、歯科で処方されることの多い「痛み止め」と「抗菌薬」について、
使われる理由や服用時の注意点などをわかりやすくご紹介します。
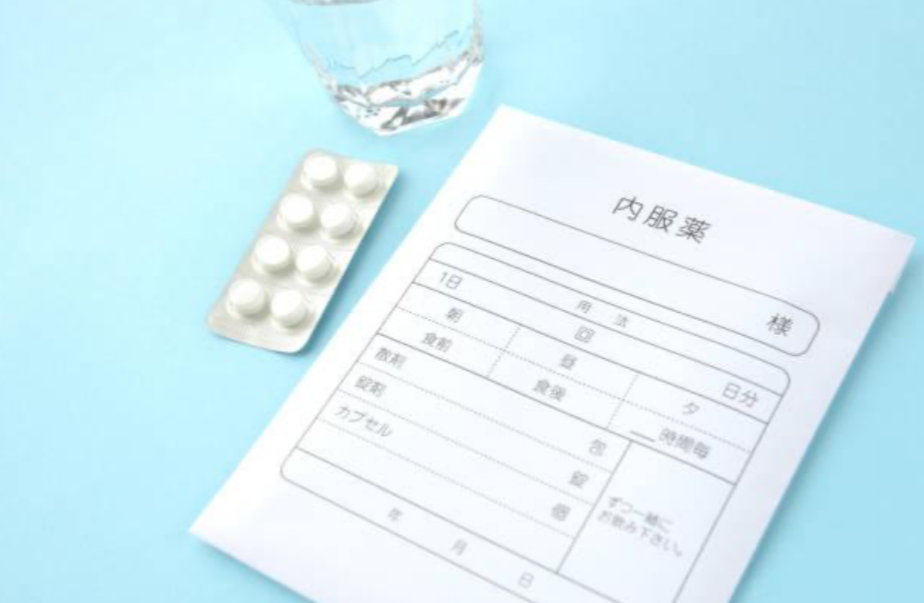
歯科で出される「痛み止め」ってどんな薬?
歯科で使われる痛み止めの多くは、「消炎鎮痛薬」と呼ばれる薬です。
なかでもよく使われるのが、ロキソプロフェン(市販名:ロキソニン)や
アセトアミノフェンなどです。
これらの薬は、痛みだけでなく、炎症や腫れを抑える働きがあります。
たとえば、歯を抜いたあとや、神経を取ったあとのように、
一時的に痛みや腫れが出やすい処置の後に処方されることが多いです。
痛み止めは、症状の強さに応じて使用の頻度や種類を調整することもあります。
医師の指示に従って、必要なときに服用するようにしましょう。
抗菌薬(抗生物質)ってどんな薬?
抗菌薬(いわゆる抗生物質)は、細菌による感染を抑えるために使われる薬です。
炎症を抑える薬と誤解されがちですが、「感染対策」が目的です。
歯ぐきの腫れや膿があるとき、親知らず周囲に炎症があるとき、
または抜歯などで細菌感染のリスクが高まる処置のあとなどに処方されます。
よく使われる抗菌薬には、アモキシシリンやセフェム系抗菌薬などがあり、
体質や症状によって使い分けられます。服用によって症状が軽くなることも多いですが、
効果を出すには決められた期間・回数を守ることがとても重要です。
どんなときに薬が処方されるの?
歯科で痛み止めや抗菌薬が処方されるのは、以下のようなケースが多いです。

痛み止め
・親知らずやむし歯の抜歯後
・神経を取る処置の後
・歯ぐきの切開など外科的処置後
・強い炎症がある場合
抗菌薬
・歯ぐきが腫れて膿が出ているとき
・歯の根の先に感染があるとき
・免疫が下がっていて感染リスクが高いとき
・抜歯など感染予防が必要な外科処置後
どちらも、「症状」や「治療内容」に応じて医師が判断して処方するものです。
自己判断で飲む薬ではないため、市販薬で代用せず、
必ず診察を受けてから処方されたものを使用しましょう。
痛み止めと抗菌薬それぞれ服用するときの注意点

痛み止めの場合
・空腹時は避けて服用(胃への負担を軽減)
・効き始めるまでに30分〜1時間ほどかかることが多いです
・症状が落ち着いていれば、無理に飲み続ける必要はありません
抗菌薬の場合
・指定された日数・回数を必ず守ること(中途半端にやめると菌が残ってしまうことがあります)
・飲み忘れた場合は、気づいた時点で1回分だけ飲み、2回分まとめては絶対に飲まない
・服用中に発疹・下痢・吐き気などの症状が出た場合は、早めにご連絡ください
また、どちらの薬も「以前もらったものを取っておいて、あとでまた使う」のは避けてください。
同じ症状に見えても、原因が異なることがあるためです。
まとめ
歯科で処方される「痛み止め」と「抗菌薬」には、それぞれ明確な目的があります。
「とりあえずもらったから飲む」「自己判断でやめる・残す」といった使い方では、
効果が十分に得られないばかりか、症状が悪化したり、副作用が出る可能性もあります。
正しく服用することが、治療をスムーズに進める大切な一歩です。
薬についてわからないことや不安なことがあれば、どうぞ遠慮なくお気軽にご相談ください。
日付: 2025年10月3日 カテゴリ:お知らせ, スタッフブログ, 歯医者さんでもらう「痛み止め」と「抗菌薬」ってどんな薬?使い方と注意点